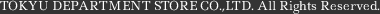お中元の熨斗(のし)の正しいマナーとは|
のし紙に関する気になる疑問

毎年お中元を贈っていても、熨斗(のし)のマナーを確認していない方は多いのではないでしょうか。せっかく相手に心を込めた贈り物をするのですから、正しい熨斗(のし)の用い方を身につけたいですね。
そこで本記事では、お中元に掛ける熨斗(のし)の正しいマナーについて詳しく解説します。熨斗(のし)に詳しくなると、目上の方へのお中元も安心して贈れるようになるでしょう。
表書きの実例も載せていますので、ぜひ参考にしてください。
お中元ののし紙に関する気になる疑問

のし紙についての基本的なマナーを理解しても、「こういう場合はどうするのだろう?」と気になる疑問もあるでしょう。お中元は古くからある風習なので、時代の移り変わりとともに変わっている決まりもあるかもしれません。
そこで、特に疑問を感じる3点について解説します。
喪中の場合、のし紙はつける?
喪中の場合はのし紙はつけません。のしや水引にはお祝いの意味が込められているため、喪中には向かないからです。
代わりに白無地の奉書紙や白い短冊をつけましょう。表書きに「お中元」または「御中元」と書くと喪中に配慮したお中元になります。
また、自身が喪中の場合はのし紙をつけて贈っても失礼にあたりません。今までと変わらないお付き合いを心がけるとよいでしょう。
フェルトペンで表書きを書くのは失礼にあたる?
本来、毛筆で書くのが望ましい表書きですが、近年はお中元の簡易化の傾向から、フェルトペンで書いても失礼にはあたらなくなっています。表書きはきれいで読みやすい字を心がけ、相手への感謝の気持ちを込めて書きましょう。
なお、ボールペンや鉛筆、黒ではないペンの使用は失礼にあたるため、使用は控えましょう。
短冊熨斗(のし)を使用しても問題ない?
短冊熨斗(のし)とは略式ののし紙で、本来であればお中元には向きません。しかし、近年はエコロジーの観点から略式も容認するべきではないかという流れがあるのも事実です。
ただし、短冊熨斗(のし)が略式である点は変わりないため、贈る相手の立場や関係性を考慮して取り入れるか考える必要があるでしょう。時代に合わせて柔軟に対応する姿勢も大切ですが、相手への気遣いや礼儀が両立するような配慮が必要です。
のし紙を正しく使って気持ちのよいお付き合いを
のし紙はお中元やお歳暮、お祝いごとの贈答品に使うため、正しいマナーを知っておく必要があります。目上の方や感謝の気持ちを伝えたい相手だからこそ、マナーはしっかりおさえておきましょう。
のし紙の文化は時代とともに変化しています。マナーに迷ったら基本に立ち返り、その都度許容範囲なのか調べましょう。
お中元に欠かせないのは相手への敬意と配慮です。贈られた側が気持ちよく受け取れるようなお付き合いを目指しましょう。