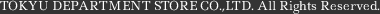お中元のマナーは知っておいて損はない!
マナーについてのよくある質問

「お中元ってなんとなく贈っているけれど、正しいマナーを知らないな」
「お中元を頂いたときのお礼のマナーを知りたい」
このように感じるときはありませんか?
この記事を読めば、正しいお中元のマナーがわかります。マナーをきちんと理解しておくと、お中元を贈るときだけでなく、受け取ったときも慌てずに対応できますよ。
いまさら人に聞けないお中元のマナーですが、しっかり理解しておいて損はありません。お中元を贈る前に、改めてお中元のマナーを見直してみましょう。
お中元のマナーについてのよくある質問

ここからは、お中元のマナーについてよくある質問に回答します。もしものときに慌ててしまわないよう「こんなときはどうすればよいのか」を把握しておきましょう。
お中元の時期が過ぎてしまったらどうすればいい?
「贈る時期は地域によって違う」でお伝えしたように、お中元は地域によって贈る時期が異なります。もし贈る時期が過ぎてしまった場合は、暑中見舞いや残暑見舞いとして贈りましょう。この際、目上の方へ贈るときは、表書きを「暑中伺い」「残暑伺い」とするのがマナーです。
暑中見舞い・残暑見舞いを贈る時期は、下記の通りです。
| 表書き | 時期 |
|---|---|
| 暑中伺い | 梅雨明け~8月7日ごろ |
| 残暑伺い | 8月7日ごろ~8月31日 |
暑中見舞いや残暑見舞いも、贈る時期が決まっています。「お中元の時期は過ぎてしまったが、感謝の気持ちを伝えたい」と考えているときは、上記の時期を参考に表書きを変えて贈り物をしましょう。
喪中のときはどうすればいい?
相手、自分どちらが喪中の場合でもお中元は贈れます。なぜなら、相手への感謝の気持ちを込めて贈る品物なので、喪中でも問題ないからです。
気になる場合は、相手に問い合わせてみると安心です。いずれにしても、お互いが不快な気持ちにならなければ、お中元のやり取りを行うのは問題ありません。
贈ってはいけない品物はあるの?
お中元には、贈ってはいけない品物があります。正確には、お中元に限らずお歳暮でも贈らないほうがよいとされている品物です。
お中元やお歳暮で避けたほうがよい品物は、下記の通りです。
- 足で踏みつけるもの・・・靴やスリッパ、靴下など
- 数字の4や9の語呂に関係するもの・・・クシなど
- 刃物類・・・包丁、ハサミなど
- 手切れを意味するもの・・・ハンカチなど
マナー違反にならないように、贈る品物には気を付けましょう。
お中元を辞めたいときはどうすればいい?
お中元やお歳暮は、最低でも3年間は贈り続けるのがマナーです。引越しや転職などで関係性が薄くなってしまった相手でも、3年間は贈り物を続けたほうがよいでしょう。
3年未満で辞めたい場合には、お中元をやめてお歳暮のみを贈るようにしてください。これは、お中元よりもお歳暮の方を重視している方が多いためです。
ただし、突然お付き合いをやめるのではなく、挨拶状に辞退する旨を記載したり、暑中見舞いのハガキをだしたりと失礼のないように対応しましょう。
お中元はマナーを理解して気持ちのよいお付き合いをしよう
お中元のマナーをまとめます。
- お中元を贈るときは、地域によって時期が異なるので気を付ける
- お中元の「のし紙」に使う水引は紅白蝶結びが基本
- お中元を受け取ったときは、お礼の連絡を必ずする
お中元のマナーは、それほど難しいものではありません。お中元に適した贈り物や贈り方に困ったときは、贈る相手やお店の人に相談してみるのもよいでしょう。
お中元は、相手への感謝の気持ちをあらわす贈り物です。マナーを重んじたお中元を通して、気持ちのよいお付き合いをしましょう。